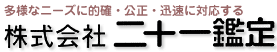不動産証券化の評価
Ⅰ.最近の不動産証券化市場の状況
J-REIT市場は平成19年前半までは海外からの投資マネーの流入などを背景に拡大を続け、上場銘柄は41銘柄、時価総額は約6.8兆円にまで達した。運用不動産の種類としても、従来のオフィス・商業施設・賃貸マンションだけでなく、物流施設やホテル、さらには工場・研究開発施設やインフラ施設と広がりを見せた。
しかし、平成19年後半にはサブプライムローン問題が引き金となり東証REIT指数は下落局面に転じ、平成20年9月のリーマンブラザーズの破綻を機に下落傾向に一層の拍車がかかり、既存J-REITでは投資口価格の低迷による増資の困難性等から新規の物件取得ができなくなっていた。また、東証の上場審査のハードルが高くなったこともあり、新規上場の延期や断念が相次ぎ、平成20年10月にはJ-REITの1銘柄が初めて民事再生法の適用を申請し経営破綻した。J-REITは不動産賃貸事業に特化していることから一般の不動産会社と異なり事業内容に関するリスクは低く、財務面でもJ-REITの負債比率は50%程度であり経営破綻リスクは小さいと考えられていたため、不動産証券化市場に大きな衝撃を与えた。平成19年末に約5.1兆円あった時価総額は平成20年10月時点では約2.5兆円にまで下落した。平成21年以降はJ-REITの公募投資法人債の発行や不動産市場安定化ファンドによる融資によりJ-REITの資金調達環境の改善、さらにスポンサー変更やM&Aを通じた再編等が行われた。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに起因する一連の東日本大震災の影響から、東証REIT指数は急落したものの、同年4月には震災前の水準に回復した。その後の東証REIT指数の動きは、欧州債務危機・世界景気減速による不動産市況の回復遅れに対する懸念や投資家のリスク回避姿勢等を受け一進一退を繰り返していた。
平成24年12月の政権交代後、アベノミクスと呼ばれる政府の経済政策や日銀の財政政策のもと円高是正及びデフレ脱却など景気の回復期待から、東証REIT指数は急騰し平成25年3月末には約1,700ポイントと5年ぶりの水準となった。その後、利益確定など市場は調整局面にあったが、平成26年4月以降は、不動産市況の回復期待・円安及び株高・日銀の追加緩和等を背景に東証REIT指数は平成27年1月には2,000ポイントに迫る勢いとなった。その後やや下落基調となったが、平成29年秋以降は上昇傾向で令和元年7月末時点の東証REIT指数は2,017.48ポイントとなっており、マイナス金利の継続等の金融政策の行方が注目される。平成30年は4銘柄が東京証券取引所に新規上場、平成31年に入ってからも2銘柄が新規上場、令和元年7月末日時点では63銘柄を数えるまでになっている。近年の上場で目立つのはヘルスケア施設やホテル・物流施設に特化したJ-REITであり、今後も留意が必要である。なお、令和元年7月末時点では時価総額が15.2兆円となっている。
他方、株式市場への上場を前提としない私募ファンドについては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所の「不動産私募ファンドに関する実態調査 2019年1月」によれば、平成30年12月末時点の運用資産額は約17.7兆円(前年比+5.1%)となっている。リーマン・ショック後、平成26年まで一貫して減少した後、平成27年から増加に転じ、平成30年も市場規模の拡大が継続した。
Ⅱ.不動産証券化における鑑定評価の留意点
1.オフォスビル・賃貸マンション
不動産の証券化における不動産の鑑定評価は、投資家の投資判断基準となるものであり、極めて重要である。今まで以上に多数のデータによる市場分析により、適正なキャッシュフローの査定が求められる。投資家保護の観点から対象不動産の収益力を適切に反映した収益価格に基づいた投資採算価値を求める必要があり、具体的には、DCF法による収益価格が標準となる。但し、現実には将来のキャッシュフローや転売価格を予測することは難しい。なぜなら、日本独特の賃貸借取引慣行があるからである。借地借家法によって借地人・借家人は保護されており、テナントの中途解約が比較的自由に出来るため、精度の高い中長期的な収益予測が困難である。オフィスビル、賃貸マンションの証券化においては、周辺の賃料相場、空室率の査定のみならず、類似不動産の取引利回りを参考にした直接還元法による検証、比準価格・積算価格による補完が必要である。
2.商業施設
商業施設は、中途解約ペナルティー付定期借家権、特に郊外型ロードサイド店舗は、事業用定期借地権が締結されている場合があり、一見長期のキャッシュフロー予測が容易であるように思える。しかし、一般に商業施設は、出店競争・価格競争が激しく、営業収益が立地条件に大きく左右されたり、建物の内装の陳腐化がオフィスビル・賃貸マンションより早い傾向にあるため、営業収益を維持するための設備投資額をDCF法におけるキャッシュフロー予測に織り込む必要がある。また、経営能力等のソフト面も重要であり、家賃が売上高に連動している借家契約も多い。周辺家賃相場に基づく家賃負担力の査定が重要であるため、商圏内で競合する商業施設・把握可能な新規出店情報等の商圏分析・マーケティングを行うことが重要である。
3.ホテル
一口にホテルといっても様々な形態があり、シティーホテル・ビジネスホテル・カプセルホテル・モーテル・温泉旅館等がある。欧米のホテルは宿泊部門が売上の主体となっている。また、日本のホテルの場合でも、シティーホテル・温泉旅館以外は宿泊部門が売上の主体となっているが、シティーホテル・温泉旅館は宴会・料飲部門が売上の主体となっている場合も多い。宿泊部門が売上の大半を占めるビジネスホテル・モーテル等は、競合ホテルの進出等の特別な要因がなければ、毎期の売上高に大きな変動が見られないことが一般的であるが、宴会・料飲部門はいわゆる「水物」であり、それが売上の主体となっているシティーホテル・温泉旅館は、景気変動の影響を受けやすい体質にある。よって、シティーホテル・温泉旅館については、欧米流の利回り・売上予測手法をそのまま利用することは妥当ではなく、法人企業等の需要予測、結婚式場・レストラン・専門店等との競合状況を分析し、宴会・料飲部門売上高の適正な査定が重要である。また、郊外型ロードサイド店舗と同様に経営能力等のソフト面だけでなく、内外装が陳腐化していないか、設備が定期的に更新されているか等の確認も重要である。なぜなら、防災安全基準・環境基準を逸脱した物件は、ノンリコースローンによる資金調達は一般的に不可能であるからである。
編集者: 不動産鑑定士 神岡 禎高